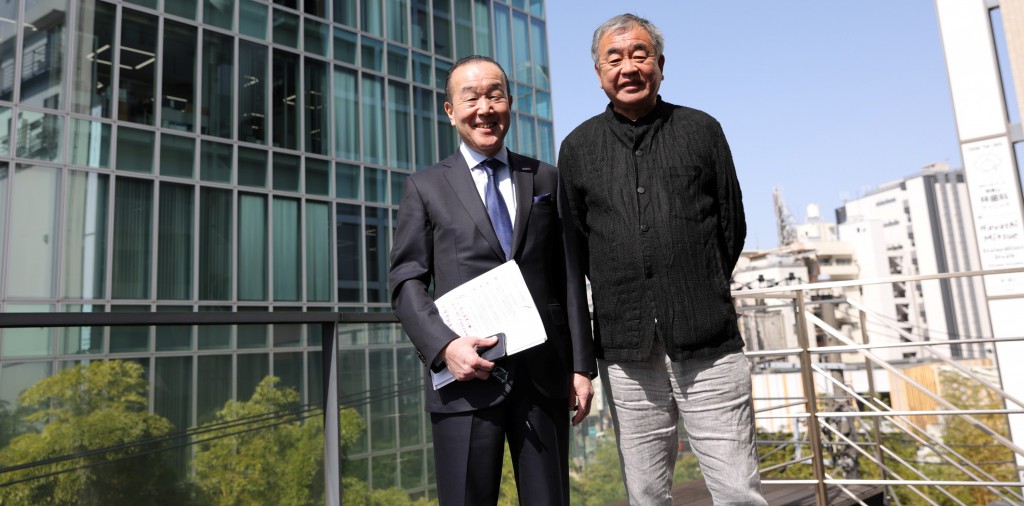REPORTレポート
デジタル化の加速とそれに伴う「業界」の消滅、米中摩擦を背景にした地政学上の変化など、今は数年先を見通すことも難しい「VUCA」(ブーカ:変動性・不確実性・複雑性・曖昧性)の時代です。その中にあって、一流の経営者や専門家は寸暇を惜しんで情報を集め、思索し、仮説検証を繰り返す中で来たるべき未来に対応しようとしています。
建設プロジェクトマネジメントや社会インフラPPP(官民連携)など、新しい市場を切り開いてきた植村が、それぞれの業界でトップを張る人々との対話を通して、建設・不動産業界のみならず日本経済や世界経済の未来、言い換えれば、暗闇の中にある一筋の光を見出していきます。
今回は国立競技場の設計に携わるなど、世界を舞台に活躍する建築家の隈研吾氏に話を聞きました。
──新型コロナウイルスの感染拡大によって、われわれの生活スタイルや行動様式は大きく変わっています。建物のあり方が人々の生活や行動の影響を受けると考えれば、建築もまた新型コロナの影響を受けているように思います。新型コロナの影響をどう考えていますか。
隈研吾氏(以下、隈):今回のパンデミックは、人類、すなわちホモ・サピエンスの歴史にとって一種の折り返し地点のようなものだと考えています。
──どういうことでしょうか。
隈:これまでは、一言でいえば「集中」というベクトルですべてが動いていたように思います。建築の世界でいえば、集中する場所としての都市があり、都市が不足すれば都市をつくるという一方向のベクトルで成り立ってきました。そういった方向に対して、精神的にも肉体的にもストレスを感じる人々はコロナ前からたくさんいましたが、今回のコロナをきっかけに、多くの人が「これまでのやり方は限界ではないか」と感じ始めた。人類が皆、同じ危機感を持ち、自分たちの行く末を真剣に心配したという意味において、歴史に刻印される大きな折り返し点になるでしょう。
実は、世の中の大きな流れは、集中ではなく自律分散の方向に向かっていると思うんです。実際、パンデミックの前から、集中への流れに逆らい人々の自律分散を可能にする技術としてAI(人工知能)が発達してきました。でも、人間自身が昔の惰性に囚われて決断を先送りにしていた矢先に、自然や災害によって人類が決断を強いられた。そんな気がします。
──働き方や企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)、自然との共生など、従来から叫ばれてきた変化がパンデミックによって一気に加速した感があります。建築や街づくりの分野はパンデミックによってどのように変わっていくと隈さんはお考えでしょうか。
隈:建築の分野では、都市の中心部に建物を建て、それをどんどん高層化していくという「箱型モデル」が中心でした。その箱型モデルを突き詰めるだけで、建築のあり方を真剣に模索してこなかったように思います。
今の箱型モデルは、実は建築の歴史でいうと本当に短く、20世紀にニューヨークで確立されました。それ以前は、それぞれの地方で、その地方の素材を活用し、それぞれの環境にあった建物を建てていましたが、20世紀に一律で集中型の箱型モデルが広まったことで、それ以外の解を全部排除してしまった。そういう箱型モデルに限界がきたということです。
ただ、今は都市一極集中の箱型モデルに代わる解を真剣に皆が探し始めたように思います。そういった意味では非常にいいきっかけをパンデミックは与えてくれたと感じています。
──箱型モデルに変わる解は見えていますか?
隈:コンピューターの世界では自律分散という言葉がずいぶん前から言われ始めています。PCやスマホなど小さなものを個人が持つことで自律分散的に生活することが可能であり、自律分散している方がむしろ集中しているよりも効率的で、気持ちよく仕事をすることができるということは情報の分野ではもはや常識です。
それでは、建築では自律分散が可能なのか。そのモデルは昔の建築の中にあるような気がしています。日本の伝統的建築というのは、実は自律分散型の非常にいいモデルで、箱として完結しないで、自然とうまい関係を保ちながら人間が気持ちよく生活できるという特徴があります。そういうモデルが歴史の中にはいろいろあるので、もう1回掘り起こし、現代の新しい技術が組み合わさった先に、集中型を超える新しい建築モデルがあるんじゃないかと感じています。
──箱型モデルは建物や街の収益力を最大化させるという意味で、極めて資本主義に適応した形だと思います。事実、企業やファンドも箱型モデルを前提にビジネスモデルを組み立てています。分散型になればなるほど一つの建物の収益力は落ちる可能性がありますが、うまく分散型にシフトしていくでしょうか。
隈:消費者の変化に伴って、効率に対する企業の考え方は変わってきているように感じます。今の消費者は、単なる企業の表面的な価値を見るのではなく、どういう企業のものを買うか、どういう企業を応援するかなど、企業の持つビジョンや哲学、社会との向き合い方を見始めています。その中で、効率的な従来型の都市型タワーを建てても消費者の共感を得ることはできないでしょう。
世間の共感を得られるような提案を出すためには、その地域、その場所でどういう貢献ができるかということを真剣に考える必要がある。社会に対する向き合い方が直接消費者に伝わる今の時代に重要なのは、その企業が持つ「心」です。私は、消費者の変化が箱型モデルに変化を促していくと見ています。
──地方の街づくりはどのように変わっていくと思いますか。
隈:地方の街づくりを振り返れば、モデルはあくまでも大都市であり、それをただコピーしていただけでした。このスタンスを根本的に変える必要性があると思います。言い換えれば、東京との関係で考えるのではなく、地方同士のつながり、あるいはその土地の環境と建築の関係性に目を向けて、今までの東京集中型を一度考え直すことが求められる。
──それではオフィスはいかがでしょう。パンデミックの結果、働き方の自律分散も加速しています。
隈:オフィス専用のビルをつくり、閉じた環境に人を詰め込めば効率的に働くという考え方も20世紀モデルです。20世紀には工場という一つの空間に人を詰め込み、効率的に作業させる工場モデルが広く普及しました。知的労働にも同じ発想を適用したのが今のオフィスビルです。こういった発想はもう考え直した方がいい。
それ以前の働き方にはもっと多様性があり、居住と労働の関係も連続的につながっていました。日本には、町家に住みながら働くという文化があり、そのライフスタイルに憧れを感じる人は今もたくさんいます。住みながら働くというのは、日本だけでなく世界でも一般的でした。
そもそもホモ・サピエンスは一つの環境に閉じ込められるのを嫌う傾向にあります。季節の移り変わりとともに変化する食べ物を求めて少しずつ移動し、場所を変え、気分を変えた。それが健康のためにもなったし、移動がコミュニケーションとコミュニティを活性化させたという面もある。どうも僕らはそういったスタイルを20世紀に入ってから忘れちゃったんじゃないかという気がします。
──街づくりという点では国が進めるスーパーシティもあります。
隈:スマートシティやスーパーシティと言われているものは、ほとんどが20世紀型の都市を前提にしていると思います。都市の中の効率を追求しているという点でもそうですし、プライバシーとの引き換えで高度なサービスが得られるという点もそうでしょう。これは20世紀型からの解放ではなく、20世紀というフレームの中での効率の進化であって、結果的にそれが自分たちの自由を奪ってしまうんじゃないかと、みんなどこかで危惧している。スマートシティやスーパーシティが今ひとつ盛り上がらないのは、その辺に理由があるような気がします。
そうではなく、スマートシティやスーパーシティが僕らを自由にしてくれる、もう一度自然と僕らをつなぎ直してくれるものなんだ、というイメージの絵が描けるかどうか。それができれば、スマートシティやスーパーシティに対する見方も変わるのではないでしょうか。
──現状では、スマートシティで顔認証のスタンダードをどの国がつくるかというような議論が中心になっていますね。AIや自動運転、5Gや6Gなど個別のテクノロジーにどうしても目が行ってしまいますが、隈さんが指摘されるように、環境と共生した新しい都市、あるいは「ここに住みたい」「ここで仕事をしたい」という人間の根源的な欲求を踏まえた街づくりが必要なのは間違いありません。
隈:そういう意味でいうと、都市というハードとITの連携がまだまだ足りないと思うんですよね。ただ、ハードを前提とした切り口でITサービスを考えると、「そんなサービスは必要ない」とみんなが思うようなサービスになってしまう傾向にある。そうではなく、新しいITサービスが街のハードや風景を変えていくという逆のベクトルで考えることが必要だと思います。現状、ハードとITの連携はまだ弱いと感じていますが、それはハード側の人間の頭の固さによるところが大きい。
 (写真:村田和聡、他同)
(写真:村田和聡、他同)──2020年9月に、フランスの思想家・経済学者のジャック・アタリ氏を招いたシンポジウムを開催しました。隈さんもパネリストとして、パネルディスカッションにご参加いただきました。この時に、アタリさんが提唱している「命の経済」(医療や食料、教育、研究開発、カーボンフリーなエネルギーなどこれからの社会で必要とされる産業全般を指した言葉)に関連して、隈さんも「命の建築」という言葉を挙げていました。
隈:もともとアタリ氏にずっと関心を持っていましたが、アタリ氏が僕の仕事に興味を持ってくれて、数年前に一緒に仕事をしたことがあります。その時に、命と人工物の親和性や、日本特有の自然が僕の建築の中に感じられると言ってくださって。アタリ氏は、ヨーロッパ的なものに限界を感じていると感じました。
欧州の知性であるアタリ氏がそういう方向性に舵を切ろうとしている。しかも、日本を評価している中で、日本人自身が日本の良さに気づいていないということを僕は残念に思います。欧州人と日本人が議論する機会を持てば、今まで気づかなかった日本の良さや可能性に気づけると思うのですが・・・。
──アタリさんはシンポジウムの場で、GAFAMのような巨大企業がいずれは国を超えるだろうと指摘していました。ただ、これからの時代は国と民間企業が対立するのではなく、それぞれが連携し、最適解を見出していく必要があると思います。建築や街づくりにおける官民連携という点ではどのように捉えているでしょうか。
隈:民の力が国家を超える力を持つ時代にもかかわらず、官は時代に即した民との新しい連携を探るわけでもなく、ただ漫然と見ているだけということが多いような気がしています。行政も政治家も、今の情勢にどうコミットするかという意識を持っていないのではないかと僕は思っています。
海外で仕事をしていると、全員とは言いませんが、それぞれの国の官僚は意識が高く、民との新しい連携を模索している人がとても多いと感じています。建築における新しい発想は、官の規制からだけでも、民からだけでも生まれず、両者がコラボレーションすることで生まれるという意識を私は持っています。これからは官民連携の中からしか、新しくて面白い建築は出ない。
そう思っているので、官民連携についてはいろいろと見ています。
例えば、デンマークの公共プロジェクトをやった時など、税金である予算の使い方に対する目は極めて厳しいものがありました。もちろん日本も厳しいですが、欧州は日本以上に税金の使い道については意識が高い。もっとも、ただ単に厳しいだけでなく、民が逆に官をサポートするんです。このプロジェクトは街の経済活性化にとってとても重要だから今以上の予算が必要だ。そのために、ファンドを通して民間がサポートしよう、と。
──どのようなプロジェクトだったのでしょうか。
隈:コペンハーゲンの中心街に建設した公共総合施設「ウォーターフロント・カルチャーセンター」です。日本ではスポーツ施設のような公共施設はただの箱物になりがちですが、このカルチャーセンターはオペラハウスの隣という立地を利用し、オペラを鑑賞した後、カルチャーセンターで運動することで心と体の両方を癒やすことのできる施設として建設しました。コペンハーゲン市民の憩いの場として、おかげさまで高い評価をいただいています。こういった仕組みがもっと日本で出てくればいいなと思います。
インフラの分野でも官民連携はとても重要です。インフラは行政の所有物で、与えられた敷地に民間企業が建物を建てるという従来の発想が退屈な街になる元凶だと考えています。自動車がガソリン車からEVに、自動運転車に変わろうとしている中、道路も時代に合わせて変わっていく必要があるでしょう。その時に面白いものができるかどうかは、民間企業の知恵と発想に委ねられています。それこそが、これからの都市が抱える大きな課題です。
──われわれも海外で有料道路の官民連携(Public Private Partnership:PPP)プロジェクトを進めていますが、海外では官民連携が当たり前です。建物としてのハードとソフト、税金を投入するがゆえの公共性、そしてビジネスとしての持続可能性の3つの部分をうまくマネジメントして、官と民、そして地域社会の三方良しを実現することが欠かせません。
隈:インフラの部分では、モビリティのシフトによって道路の意味合いが変わってくる。その部分でどういうふうに民間側のパートナーが面白いものをつくれるか。それがこれからの都市で大きな課題になる。
例えば、マンハッタンのブロードウェイを歩行者専用にした時に、地元の商店は「車が通らなくなると商売が潰れる」と反対意見が起きました。でも、蓋を開けてみれば商売も税収も上がり、地域も行政もハッピーになりました。フランス・パリのシャンゼリゼ通りも4車線を2車線にして緑の空間を増やそうとしている。これからは、インフラの部分のリデザインがものすごく重要。その時に、インデックスが手がけている官民連携のプロジェクトマネジメントは意味を持つと思います。
──国土交通省ともよくお話しますが、国交省は道路局や都市局など、同じ都市に関わる分野でも局が縦割りになってしまっています。都市にまつわるあらゆるものは、一体で考えていかなければならないと感じています。
隈:そうですね。20世紀型の高度経済成長の時代には、それぞれの部署が縦割りでも全体が伸びていたのでうまく回っていました。ただ、そうやって切り分けてしまったために都市がつまらなくなっていくわけで。そのためには、植村さんがやっているようなプロジェクトマネージャーに縦割りになった領域をつないでもらう必要がある。
プロジェクトマネージャーという存在がなければ、それぞれの領域の論理で動き、それぞれの領域にボスができてしまう。建築界は典型的で、建築という領域の中で、実用性や社会がほしがっているものではなく、複雑なデザインをすることを目的に動いてしまっている。僕はそういう世界で息が詰まるような思いをしているので、領域を横断できるプロジェクトマネージャーが絶対に必要だと思っています。
現に、プロジェクトマネージャーが入っている建築は今までの建築の枠を超えるものになっています。米国は新しい種類のコンサルタントが勝手に生まれ、コンサルタントの必要性を認める社会ですが、日本はそうではありません。日本にこそプロデューサーのような人たちが出てこないと厳しい。だから植村さんには期待しています。
──隈さんはご自身が関わる建築プロジェクトでもプロジェクトマネージャーを積極的に活用しています。それはなぜでしょうか。
隈:建築家は与えられた条件の中で仕事をする傾向にあります。もちろん、建築プロジェクトには様々な制約があるので与件の中で仕事するのは当然です。ただ、その与件が少し変わればもっと面白くできると思う瞬間はたくさんあります。プロジェクトマネージャーは一番大切な与件のところをデザインするので、彼らが入ることで、従来の建築の枠を超えるようなものができるという感覚があります。僕にとって、プロジェクトマネージャーと一緒に仕事するのは極めて重要なことです。
 ──ありがとうございます(照)。先ほど「伝統的な建築を掘り起こし、現代の新しい技術が組み合わさった先に箱型を超える新しい建築モデルが生まれるのではないか」という話がありました。日本の伝統建築についてはどのようなイメージを持っていますか。
──ありがとうございます(照)。先ほど「伝統的な建築を掘り起こし、現代の新しい技術が組み合わさった先に箱型を超える新しい建築モデルが生まれるのではないか」という話がありました。日本の伝統建築についてはどのようなイメージを持っていますか。隈:日本はこれだけ小さい国なのに極めて多様性に満ちあふれています。日本の伝統的な建築はこういった多様性を生かしてきました。素材である木材についても、使っている木はそれぞれの地域によって違っていて、それぞれの木に応じて独特の使い方があったのに、戦後の植林で杉一色になってしまった。そういう木材の使い方をもう一度見直したいと思っています。
これからは日本のどこか一つに注目するのではなく、多様性に着目して地方を見直したいですね。それも、地方にただ建物をつくるのではなく、その地域に僕ら自身が入り込み、場合によっては人を送り込み、その地域の人と一体となった物づくりがしたい。現に、北海道東川町にサテライトオフィスをつくりました。今後はスタッフを常駐させる予定です。
──隈さんは大型建築において木材を生かした設計に積極的に取り組んでいます。私は材木屋の出身なので隈さんが進めている木材利用は素晴らしいことだと思います。ただ、一方でそういった需要を埋めるだけの国内産材を供給できておらず、原木を輸入に頼っているという残念な現実があります。
隈:そうなんですよね。
──林業を復活させるためには3つのサイクルを回す必要があると思います。まず、材木がちゃんと出てくる仕組みをつくる必要がありますので、オーストリアのように山に投資して、機械設備や林道の整備など林業自体を近代化させる。近場に製材所をつくることも不可欠です。次に、隈さんがご尽力されているように、公共建築や大型建築での木材利用を今以上に加速させる。最後に、林業の過程で生じる端材を活用した木質バイオマスを地方のエネルギー源として活用する。この3つのサイクルをぐるぐると回さないと林業は再生しません。
隈:役所自身が縦割りになってしまっているので、それぞれがうまく連携できていないんですよね。
──まさにその通りです。全く連携がとれていません。さて、大分長くなってきましたので最後の質問ですが、隈さんはこの2月に、隈研吾建築奨学財団という公益財団法人を設立されました。どのような想いで設立されたのでしょうか。
隈:海外で仕事をしていると、デザインの世界における日本の技術力は極めて高いものがあると感じています。ほかの分野だと言語の壁がありますが、建築の世界では言語はなく図面で伝わる部分がある。しかも、建築関連のソフトウェアは世界共通なので、境界なくぱっと外でチャレンジすることが可能です。
僕自身、20代の時にAssociation of Corporate Counselという米国の財団のおかげで、1年間米国で勉強することができました。その経験は、僕にとって大きな転機になりました。同じように若者のきっかけになるものをつくりたい、建築を志す多くの若者に海外で様々な体験をしてもらいたいと思って財団をつくりました。僕も、米国留学時代のネットワークが今も生きていますから。
──そういえば、隈さんの事務所は国籍や性別、年齢に関係なく様々な方が働いていますね。
隈:実は、意識してダイバーシティを感じられる人材を採用しています。ただ設計がうまいだけでなく、バックグラウンドを含めて「この人は面白い」「この人が加わればダイバーシティ意識が向上するんじゃないか」という点を見て評価しています。現在、私の事務所では20カ国以上の人が働いています。ここで働いている300人の半分は日本国籍以外です。
──それはすごいですね。
隈:多様性がありすぎるとマネジメントが大変という声もありますが、ここの場合は違うバックグラウンドの人間と会うことでストレスが発散されるというような、ちょうどいい空気感が生まれています。2000年前後からダイバーシティ採用を始めて、雰囲気が良くなることが分かったので、積極的に舵を切りました。
植村:世界で活躍する素晴らしい建築家を生み出されることを楽しみにしています。今日はお時間をいただきありがとうございました。
WRITERレポート執筆者
-

植村 公一
代表取締役社長
1994年に日本初の独立系プロジェクトマネジメント会社として当社設立以来、建設プロジェクトの発注者と受注者である建設会社、地域社会の「三方よし」を実現するため尽力。インフラPPPのプロジェクトマネージャーの第一人者として国内外で活躍を広げている。
その他のレポート|カテゴリから探す